6月下旬からモンゴルやキルギスなどの乗馬ツアーが出始め、今年もいよいよ夏のハイシーズンに突入しました。

先日、弊社の中村がメールマガジン「つむじかぜ」の連載コラム、“風の向くまま 気の向くまま”で、消防庁の「上級救命講習」を受講した際の記事「BE FAST」を投稿していましたが、私も夏のシーズン前の6月末の金土日で、数年ぶりに日本赤十字の救急法救急員養成講習を3日間受講してきました。

過去に受講↑した消防庁の講習も含めると、おそらく、かれこれ4-5回目になります。この講習は他人と至近距離で密接に触れ合う講習もあるため、コロナ禍中は、なかなか受講することが難しく、5年以上開けての再受講。風の旅行社スタッフは基本的に全員がこういった講習を受講しています。
今回は、
■手当の基本
■一次救命処置(心肺蘇生、AEDを用いた除細動、気道異物除去)
■急病
■けが
■止血
■きずの手当て
■骨折の手当て
■搬送
■救護
などを、教本を見ながらの講義及び試験、実技講習でみっちり学び直してきました。

以前はやっていたものが無くなっていたりもしましたが、新しく「止血帯(ターニケット)による止血法」を学ぶことも出来ました。止血帯はツアー時にも役立ちそうなので、帰宅後すぐにamazonでポチ。今週末の添乗に持参します!
尚、弊社取り扱いのツアーは、乗馬やトレッキング、登山、キャンプなどのアウトドアで活動する旅行が多いため、これまでも様々な事故に遭遇してきました。実際に自分がその場にいた経験はそれほど多くはないものの、
*乗馬中に落馬して骨折、脱臼、脳震盪
*山を歩いていて捻挫、脱臼
*マウンテンバイクで落車して大ケガ など
記憶に残っている案件だけでも相当な件数があります。
過去にモンゴルの草原のど真ん中で負傷者が出てしまった際には、手持ちの布で患部を固定してあげて痛みを軽減させる、止血するなどの手当てをまず行いました。資格だけ持っていても実際の現場で使えなければ意味がありません。いつどこで起きるかわからない、いつどこで起きても何かしらの救助が行えるよう、救急法の技術のブラッシュアップはやはり大切だなぁと常々感じている次第です。
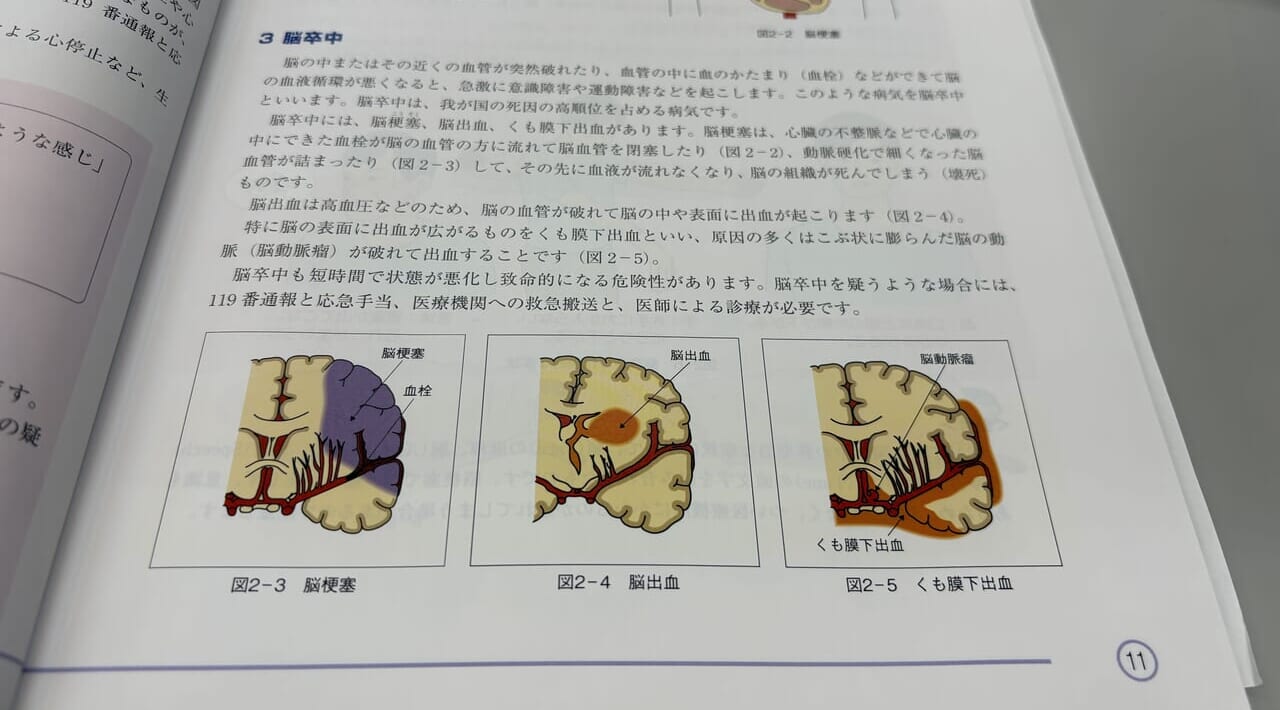
今年の3月に、弊社社内で急病者が出て、実際に救急車を呼び救急隊に引き継ぐまでの一連のシーンを今でも鮮明に覚えています。同僚の命を助けることはできなかったけれど、せめて意識(感覚)がある間は、少しでも苦痛を軽減させてあげたいと思いながらみんなで声掛けをしたり、回復体位をとらせたりしながら、その場で思いつく出来る限りの対処をしました。
実際に、自分の目の前で、急病発生から搬送までを体験したあとだと、講習のリアリティが全く違ってきます。
ツアー中に限らず、これから先、いつどこでそういった急病人に遭遇するかわからないので、今回学び直したことを出来る限り忘れずに、どこかの誰かの救急・救助に役立てたいと思います。

尚、今回参加した救急員養成講習は、地元の赤十字病院での開催。今まで参加した講習の中で一番笑いと優しさに溢れた講習で、本当に楽しく朗らかな時間でした。誰かを救いたいという気持ちがある皆さんはやはり心優しい方ばかりで、ボランティア愛に溢れたインストラクターさんたちにはただただ感謝しかありません。
講習中に、一緒にバディを組んだ22歳の女子から「扱い方がとっても優しくてノンストレスです」と、嬉しい誉め言葉をたくさん頂いたので、もし何か起きた時にも、傷病者の方にも安心感を与えられるお手当や声掛けがこれからも継続できるように努めます!