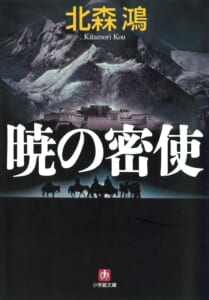 「グレート・ゲーム」とは、19世紀から20世紀初頭にかけて中央アジアの覇権を巡って展開されたイギリス帝国とロシア帝国の地政学的対立を指す言葉です。イギリス東インド会社のアーサー・コノリーが1840年に初めて使用したとされ、後に『ジャングル・ブック』で有名なノーベル賞作家ラドヤード・キップリングの小説『少年キム』 によって広く知られるようになりました。
「グレート・ゲーム」とは、19世紀から20世紀初頭にかけて中央アジアの覇権を巡って展開されたイギリス帝国とロシア帝国の地政学的対立を指す言葉です。イギリス東インド会社のアーサー・コノリーが1840年に初めて使用したとされ、後に『ジャングル・ブック』で有名なノーベル賞作家ラドヤード・キップリングの小説『少年キム』 によって広く知られるようになりました。
当時、ロシアは不凍港の確保とインド進出を目指し、中央アジア、そして極東へ勢力を拡大していました。対してイギリスは英領インドを守るためアフガニスタンを緩衝地帯にしようと画策し、またアヘン戦争をきっかけに中国(当時の清朝)へも勢力拡大を企図していました。そのため、中央アジア、極東、そしてチベットなどを舞台に対立が先鋭化していました。この対立は、英露のみならず、日本、中国、ドイツ、フランス、アメリカなど列強国も入り乱れ、情報戦・外交戦・軍事的駆け引きが複雑に絡み合い、まるでチェスのような戦略的展開を見せたため「グレート・ゲーム」と呼ばれました。日本にとっては、幕末、明治維新を経た日清・日露の戦役の時期と重なります。
先週の水野の記事と重なってしまいましたが、10月から始まった中野照男先生のオンライン連続講座「西域(シルクロード)に魅せられた探検家たち」の第1回を拝聴しました。
「グレート・ゲーム」の時代にシルクロードで日本、ドイツ、イギリス、フランス、ロシアなどの探検隊、調査隊がどのような活動をしたかを多くの資料を駆使してお話してくださる予定ですが、第1回では日本の大谷探検隊についてのお話でした。
講座で話が出たのが同時期にチベットへの潜入を企てた日本人である河口慧海や能海寛、寺本婉雅たちのこと。河口も能海も寺本も仏教僧として、廃仏毀釈の荒波を乗り越えるため純粋な宗教心から、仏教の原典を求めてチベット入りを目指しましたが、果たして彼らに政治的な背景があったのか(なかったのか)、今も研究されています。
そこで参考図書として紹介されたのが『暁の密使』(北森鴻:小学館)という能海寛を主人公にした小説です。講座を聞いてすぐに購入して興味深く読み進めています。
グレートゲームの時期から第2次大戦中にかけてチベット入りを目指した10名ほどの日本人がいますが、その一人である真宗大谷派の僧侶であった能海は四川省側から東チベット(カム地方)のパタンまで潜入したもののラサ入りは果たせず、その後雲南省からのラサ入りを目指して旅立った後、消息を絶ったとされています。2度のラサ入りを果たし有名な『チベット旅行記』を著した河口慧海のような知名度はないので、これまであまり興味を持っていなかったのですが、この小説ではグレートゲームが1つのキーワードになり、話が展開していきます。『さまよえる湖』で有名なスウェン・ヘディン、ダライ・ラマ13世の外交官だったドルジェフ、アヘン貿易で巨万の富を築いたジャーディン・マセソン社のエージェントなど気になる名前も登場します。
論文ではなく一般向けの小説として書かれているため背景説明などが分かりやすく、彼がラサ入りできず非業の死を遂げたという結末を知っているのに、先が気になって仕方ありません。3分の2ほど読み進めたところですが、果たして結末がどうなるか、この週末ゆっくり楽しみたいと思います。