

第312話 アクー ~おっちゃん~ チベット医・アムチ小川の「ヒマラヤの宝探し」
薬学部時代の筆者 修正 大学4年生の僕は有機化学合成、いわゆるケミカルの研究室に属し、合成薬の副作用を防止する研究を行っていた。このまま大学院に進学し2年後に一流製薬企業への就職が、ほとんどの東北大学薬学部生にとっての既 […]


薬学部時代の筆者 修正 大学4年生の僕は有機化学合成、いわゆるケミカルの研究室に属し、合成薬の副作用を防止する研究を行っていた。このまま大学院に進学し2年後に一流製薬企業への就職が、ほとんどの東北大学薬学部生にとっての既 […]

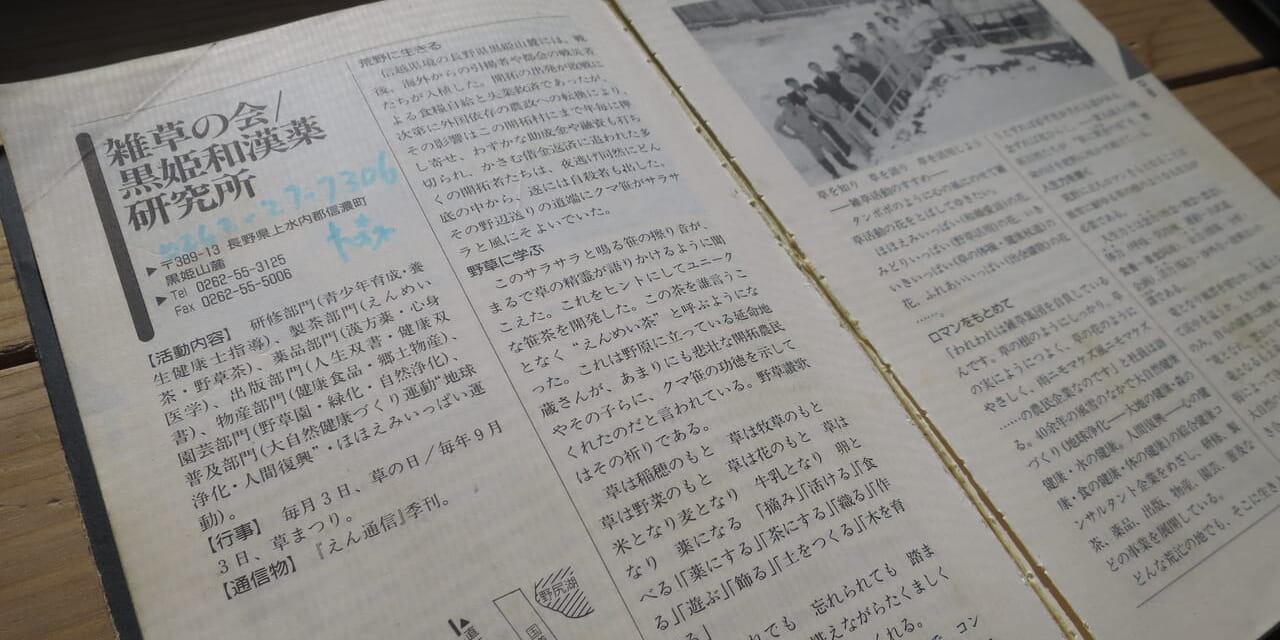
もうひとつの日本地図 佐渡の自然学園を辞めた後、居場所を失った24歳の僕はしばらく都内に住む岩(がん)さんの6畳一間のアパートに居候していた。所持金が少なく、かなりすさんでいた。そんな僕にいよいよ愛想を尽かしたのだろう、 […]


ロシアといえばマトリョーシカ ロシアはチベット語でウルソという (注1)。ただし12世紀ころに完成したチベット医学教典『四部医典』にはロシアに相当する地域は登場しない。登場するのはインドにあたるギャ(広大な)カル(白)、 […]


四部医典の絵解き図より 1980年僕が10歳のとき、はじめて東京を旅行し上野公園、東京タワーなどを観光した。しかし、それらお決まりの観光地を差しおいて、もっとも印象に残ったのは上野駅前に座っている傷痍軍人の方々だった。僕 […]

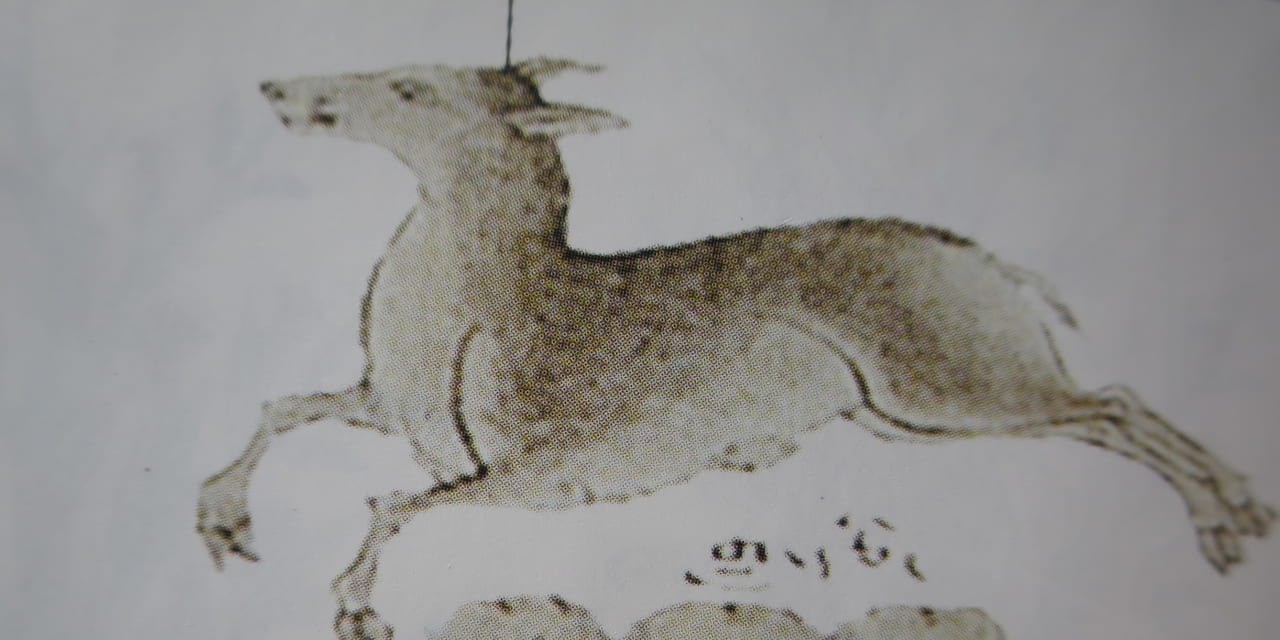
小さい頃、遠足といえばバスの酔い止めにみんな仁丹を持ってきていた。せっかく買ったのだからと、気分も悪くないのに小さな銀色の丸薬を口にすると清涼感のある香りが広がったのを覚えている。仁丹は甘草、阿仙薬、薄荷、丁子など穏やか […]


かっこいい山伏になるための薬草講座 2015年に戸隠神社で開催した「かっこいい山伏になるための薬草講座」。閃いたタイトルは我ながら面白いと思ったのだが、あいにく山伏は誰も参加してくれなかった。それでも30名近い方が参加し […]


日本藥学史 2011年、古書店で『日本藥學史』を偶然見つけた。薬学部生時代にはこの本の存在はおろか、「薬学史」という科目の存在すら知らなかったのだから誠に恥ずかしい。「印刷が甚だ困難な時代に出版を快諾せられ」という序言の […]


「ジンカ・ケワ」四部医典の絵解き図より 「喩えるならば、僕はチベット医学界の高見山です」と講演会で自己紹介すると、僕よりも年配者の方々は笑いとともに頷いてくれる。高見山(注1)といえばハワイ出身の大型力士。大相撲界初の外 […]


20歳、1990年の夏、実家のある富山県高岡市から東北大学のある仙台まで600キロの道のりをなぜ自転車で帰ろうと思ったのか、その切っ掛け・動機をまったく思い出せない。それまでまったく自転車に興味はなく、当時はいまほどに自 […]


メンツィカン(医薬暦学院。北インド・ダラムサラ)を卒業し寮生活から解放された2008年研修医の時代、毎朝ヨガ教室に通っていた。といってもそんなに大袈裟なことではなく、たまたま現地に長期滞在していた日本人ヨガ講師がボラン […]


北インドのダラムサラ 2000年の秋、亡命チベット政府がある北インド・ダラムサラで日本映画祭(日本大使館共催)が開催され、多くのチベット人が興味津々に訪れた。すべて英語の字幕がついて6本上映されたと思うが、僕の記憶に残っ […]


夕暮れの森のくすり塾 夏の暑さが増してくると、寝苦しい標高400mの自宅ではなく、冷涼な700mのお店で寝泊まりするようになる。そんな7月10日の夜10時ころ、森のくすり塾のまわりに奇妙な鳴き声が一定間隔で響き渡った。「 […]